1. はじめに
離婚に際して問題となる「財産分与」は、単なる資産の分け合いではなく、婚姻生活中の協力関係に基づいて形成された財産を公正に清算する法的制度です。とりわけ財産分与の中核をなす「清算的財産分与」については、実務上多くの争点が存在します。
本稿では、清算的財産分与の法的性質、対象財産の範囲、評価・分与の基準時、寄与割合の考え方などを簡単に解説します。
2. 清算的財産分与とは何か
民法768条1項に基づく財産分与には3つの側面があるとされていますが、実務上は婚姻中に夫婦が協力して形成した財産を公平に清算する「清算的財産分与」が中心となります。
3. 財産分与の対象となる財産とは
(1)実質的共有財産
名義にかかわらず、夫婦の協力によって取得・形成された財産が対象となります。以下のような財産が含まれます。
- 不動産(名義の如何を問わず)
- 預貯金
- 株式や有価証券
- 退職金や保険解約返戻金(支給見込額含む)
たとえば、法人名義や子名義であっても、取得原資が夫婦の協力によるものであれば、分与対象となる可能性があります。
(2)債務の扱い
夫婦の生活のために負担した債務も、実質的に共有であれば、分与において考慮されます。住宅ローン等が典型的であり、債務と担保資産をセットで評価する必要があります。
4. 対象財産の評価時点と基準
清算の実務では、次の2つの時点が重要です。
(1)分与対象の基準時:原則「別居時」
夫婦の協力関係が終了した時点、すなわち別居時が基準とされるのが実務の通例です。別居後に取得した財産については、たとえ婚姻関係が継続していても分与対象には含まれません。
(2)財産評価の時点:原則「分与時(審判時)」
対象財産の評価は、分与の実施時点(裁判であれば口頭弁論終結時)で行うのが実務の通例です。価値変動のある資産(不動産や株式など)については、特に注意が必要です。
5. 財産分与の割合(寄与度)
(1)原則は「2分の1」
家庭裁判所の実務では、双方の寄与が等しいと推定されるため、原則として2分の1ずつに分与されます(平等推定説)。
(2)寄与度に差がある場合
例外的に、次のような事情がある場合には寄与割合に差が認められます。
- 特別な資格や能力(医師、弁護士など)に基づく高収入
- 家業従事による明確な労働貢献
- 一方による浪費・隠匿行為
6. 清算方法と分与の具体的方式
清算方法としては、以下の2種類があります。
(1)金銭清算方式(原則)
財産そのものの名義は維持しつつ、差額を金銭で調整する方式。たとえば、不動産は夫が取得し、その代わり妻に金銭を支払うといった形式です。
また、対象財産を売却して売却金を分配するという方法もあります。
(2)現物分与
住宅や車など、共有財産を現物で分ける方式。共有関係の解消や今後の利用実態を踏まえて、現物分与が望ましいとされる場合もあります。
7. 実務上のポイント
財産分与においては、次の点などが重要になることが多いです。
① 分与対象の財産を特定するための資料の収集
- 金融機関の取引履歴、登記簿謄本、残高証明などを取得
② 別居時点の明確化
- 争いがある場合は、別居届や公共料金の停止、住民票の移動などの資料が必要となることも
③ 特有財産(特有出資)の主張
- 婚姻前から保有していた預貯金等の財産の立証
- 自宅の頭金を自分の特有(もしくは自分側の両親の)財産から出資していたことの立証
8. まとめ
財産分与は、単なる「分け前争い」ではなく、夫婦の協力の成果を適正に評価し、将来の経済的基盤を再構築するための制度です。財産分与は離婚後の人生設計にも直結します。事案に応じた適切な主張立証が不可欠です。
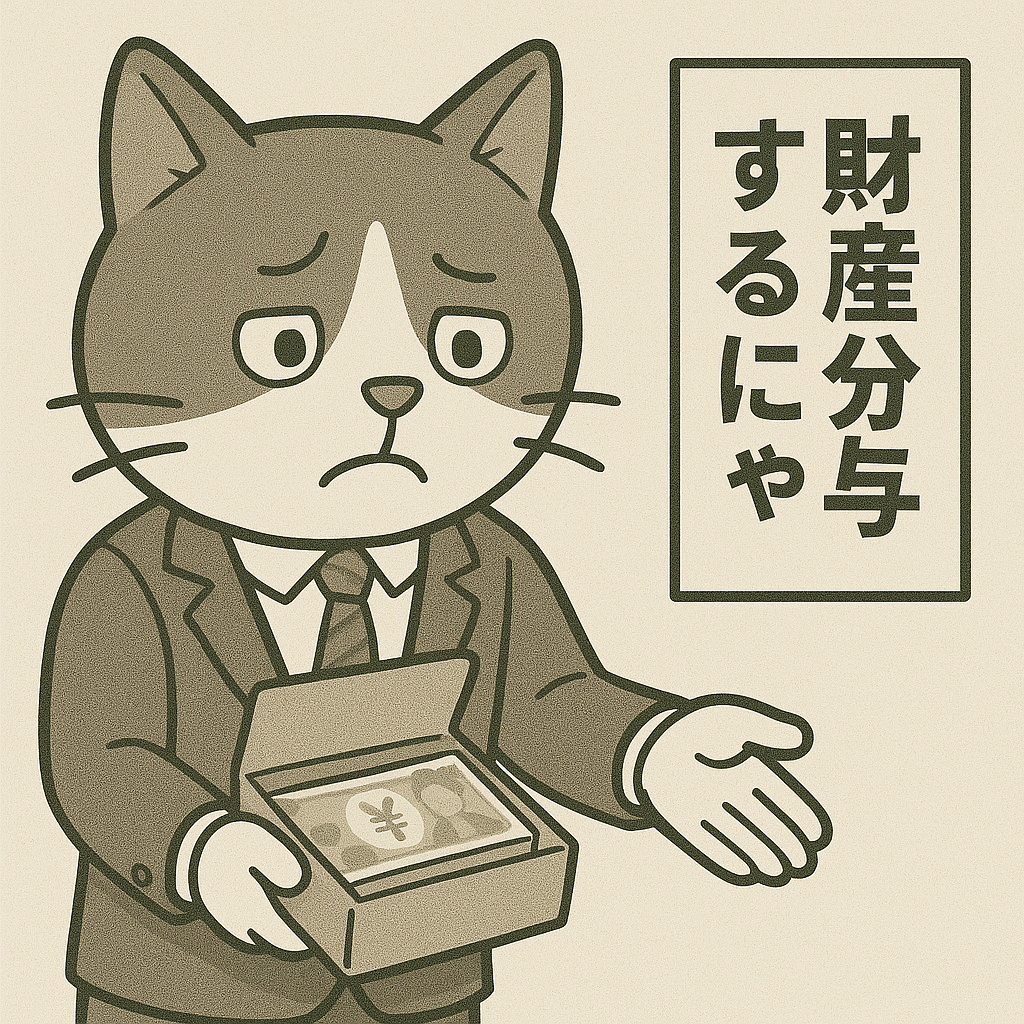


コメント