はじめに
ある日突然、自宅に「裁判所」からの郵便物が届いたとしたら──誰もが驚き、不安に駆られることでしょう。中身を確認すると「訴状」と書かれていた。こんなとき、「これは間違いでは?」「無視しても何も起こらないのでは?」と思われる方も少なくありません。
しかし、訴状は単なる通知ではなく、正式な法的手続きの始まりを告げる重要な書類です。本コラムでは、訴状を無視した場合の法的なリスク、受け取った後に取るべき行動、そしてよくある疑問点について、専門的な観点から分かりやすく解説します。
1.訴状を無視するとどうなるのか
裁判所から届く訴状は、あなたが被告として訴えられたことを通知する文書であり、これを無視すると裁判所は「被告は争う意思がない」と判断します。これにより、原告の主張をそのまま認める「欠席判決」が下される可能性があります。
欠席判決が確定すれば、原告はその判決に基づいて強制執行(例:財産や給与の差押え)を行うことが可能になります。また、いったん判決が確定すると、後から異議を唱えることは極めて困難です。したがって、訴状を受け取ったら、まずは「無視しない」ことが大前提です。
2.訴状が届いたときの対応フロー
訴状を受け取ったら、以下のような流れで対応しましょう。
(1)書類の確認
誰から、何について、どのような請求を受けているのかを整理しましょう。訴状のほかに「口頭弁論期日呼出状」や「答弁書のひな型」などが同封されています。
(2)期日の確認
呼出状には、第一回の裁判期日と、答弁書の提出期限が記載されています。この期限を過ぎてしまうと欠席扱いとなるおそれがあります。
(3)事実関係と証拠の整理
相手の主張が事実に反していると感じた場合は、反論のための資料や証拠を準備しましょう。
(4)答弁書の提出
期限内に裁判所へ答弁書を提出することで、「争う意思がある」ことを明確にできます。これにより、いきなり欠席判決が下されるリスクは回避されます。
・・・とはいえ、弁護士への相談するのが一番
訴訟対応を自身で行うのは現実的ではありません。訴訟のルールは非常に難解であり、専門家でなければ適切な対応ができないことが殆どです。そのため、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は訴状の内容を法的に分析し、今後の見通しや対応方針を助言します。
3.訴状を受領拒否すれば問題ない?
受取拒否は無意味です。訴状を受け取らなかったとしても、その後原告が一定の手続を踏めば「届いた」とみなされる場合があります。
まとめ
訴状が届いたら、まずは「落ち着くこと」、そして「無視しないこと」が最も重要です。対応を誤ると、思いがけない不利益を被るおそれがあります。早期に弁護士へ相談することで、適切な対応と今後の見通しを把握でき、不安を解消する第一歩となるでしょう。
突然の訴状にも、冷静に、そして適切に対応することで、あなたの権利と利益を守ることができます。
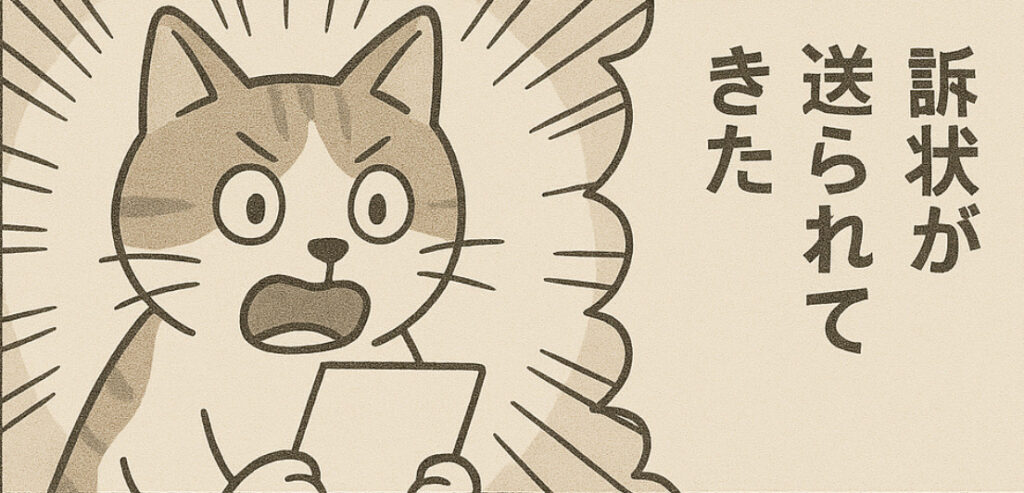
※正式に依頼するかはさておき、まずは弁護士に相談してくださいね。事案の類型によっては無料相談が可能な法律事務所も多いですよ。
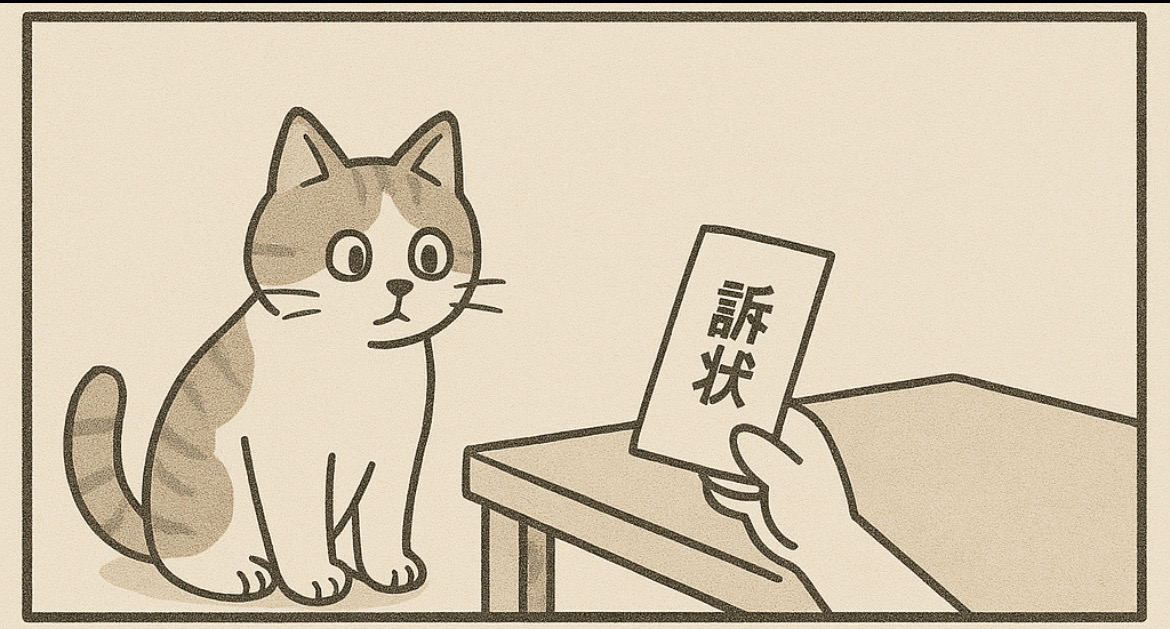


コメント