はじめに
「窃盗罪」と聞くと、どこか遠い世界の話のように感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、窃盗は私たちの暮らしのすぐそばに存在する非常に身近な犯罪であり、警察庁の統計によれば、刑法犯全体の中でも最も多い割合を占めています。
万引き、自転車の持ち去り、職場等における備品の持ち出し──こうした行為は、たとえ軽い気持ちだったとしても、すべて窃盗罪に該当し得るものです。本コラムでは、窃盗罪がどのような犯罪であるのか、成立の条件、処罰、具体的なケース、そして被害者・加害者の立場から取るべき対応について、わかりやすく解説いたします。
窃盗罪の定義(刑法第235条)
日本の刑法において窃盗罪は、刑法第235条に規定されています。同条文では、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する」と定められています。
ここでいう「窃取」とは、他人が占有する物を、その意思に反して自己または第三者の支配下に置くこと、すなわち無断で盗み取ることを指します。盗まれる対象である「財物」は、物理的な財産である必要があります。
なお、盗まれた物に高い価値があるか否かは、基本的には犯罪の成立に影響を与えません。たとえ100円のお菓子であっても、占有者の承諾なく持ち去れば、窃盗罪として成立する可能性があります。
窃盗罪が成立するための要件
窃盗罪は、単に「他人の物を取った」というだけでは必ずしも成立しません。刑法上の犯罪は一定の要件(構成要件)を満たす必要があり、窃盗罪については主に以下の4点がポイントとなります。
他人の占有する財物であること
対象となる財物は、他人の占有下にあるものでなければなりません。なお、他人に貸している自分の物であっても、相手の同意を得ずに取り戻せば窃盗罪が成立し得るのです。
占有者の意思に反して占有を侵害すること
財物の占有者がその物を事実上支配している状況下において、その意思に反して物を取り去る行為が「窃取」です。持ち主やお店の目を盗んで行うことが典型例です。目の前で奪い取った場合は強盗や恐喝など、別の犯罪が成立する場合もあります。
故意があること
誤って他人の物を持ち帰ってしまったようなケースでは、故意(意図的な意思)がないため、窃盗罪は成立しません。盗むつもりでなければ処罰の対象にはなりませんが、過失であっても民事上の責任を問われることはあり得ます。
不法領得の意思
不法領得の意思とは、窃盗罪などの財産犯において、行為者が他人の財物を自己のために利用・処分する目的(経済的用益の享受)で奪う意思をいいます。たとえば、他人の自転車や私物を、その人に対する嫌がらせの目的で別の場所に移動させたが、使用や処分の意思はなかったという場合には、不法領得の意思を欠き、窃盗罪は成立しない可能性が高いです。
処罰の内容と量刑の傾向
窃盗罪に科される刑罰は、前述のとおり「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。これにより、事案の軽重に応じて、刑事罰の内容に大きな幅が生じることになります。
初犯の場合
被害額が少なく、初犯で反省の意思が明確である場合は、起訴猶予処分、あるいは略式命令による罰金刑(正式な裁判は行わずに罰金を納めて終結)となる可能性もあります。また、正式裁判となった場合においても、執行猶予付きの懲役刑が選択されることが一般的です。
再犯・常習犯の場合
一方、過去にも同種の犯行歴がある場合は、実刑判決が下される可能性が高まります。特に、執行猶予中の再犯や、手口が悪質で計画的であった場合には、量刑が重くなります。場合によっては「盗犯等ノ防止ニ関スル法律(盗犯等防止法)」が適用され、法定刑の下限が引き上げられることもあります。
被害額が大きい場合
窃盗罪は財産犯であり、窃盗行為によって被害者が被る経済的損失の程度が、処罰の判断において重要な要素となります。被害額が大きければ大きいほど、量刑が重くなる傾向にあります。
身近に起こる窃盗の典型例
万引き
店舗に陳列された商品を、代金を支払うことなく持ち出す行為です。未成年者のみならず、高齢者や社会的地位のある人が加害者となるケースもあり、「つい出来心で…」では済まされません。
自転車の盗難
無施錠の自転車を勝手に持ち出す行為も、明白な窃盗行為です。たとえ「借りただけ」のつもりでも、所有者の許可がなければ違法行為です。
職場での持ち出し
会社の商品、金銭等を無断で持ち出す行為も、厳しく対処されることがあります。刑事責任だけでなく、懲戒解雇や損害賠償請求といった民事責任を伴うこともあります。
被害に遭ったときの対処法
万一、窃盗被害に遭ってしまった場合は、以下の手順を踏むことが推奨されます。
- 早期の通報:現場の保存と、可能であれば防犯カメラ映像などの証拠を確保。
- 被害届の提出:被害届を提出することで、警察の捜査が本格的に始まります。
- 保険の確認:被害品に保険が適用される場合、被害届の受理証が必要となることがあります。
- 再発防止策の検討:同様の被害を防ぐため、防犯設備の見直しや施錠の徹底なども有効です。
容疑をかけられた場合の留意点
一方で、自身が窃盗の容疑をかけられた場合には、以下の点を念頭に冷静な対応が求められます。
- 弁護士への相談:取調べの初期段階から弁護人の助言を受けることで、供述内容の精査や不当な取り調べの防止に繋がります。
- 黙秘権の行使:供述内容が不利に働くおそれがあるときは、黙秘権の行使も重要な判断となります。
- 示談の成立:被害者との間で示談が成立すれば、起訴猶予や処罰の軽減に繋がる可能性があります。
- 再発防止の意思表示:反省と再発防止の姿勢を明確にすることで、量刑判断に良い影響を与える場合もあります。
おわりに
窃盗は非常に身近な犯罪です。窃盗罪の成立要件や容疑をかけられた場合の対処法などを知ることで、自分や大切な人の身を守る第一歩になります。
少しでも不安や疑問をお感じの方は、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。刑事事件に精通した弁護士が迅速かつ丁寧に対応いたします。
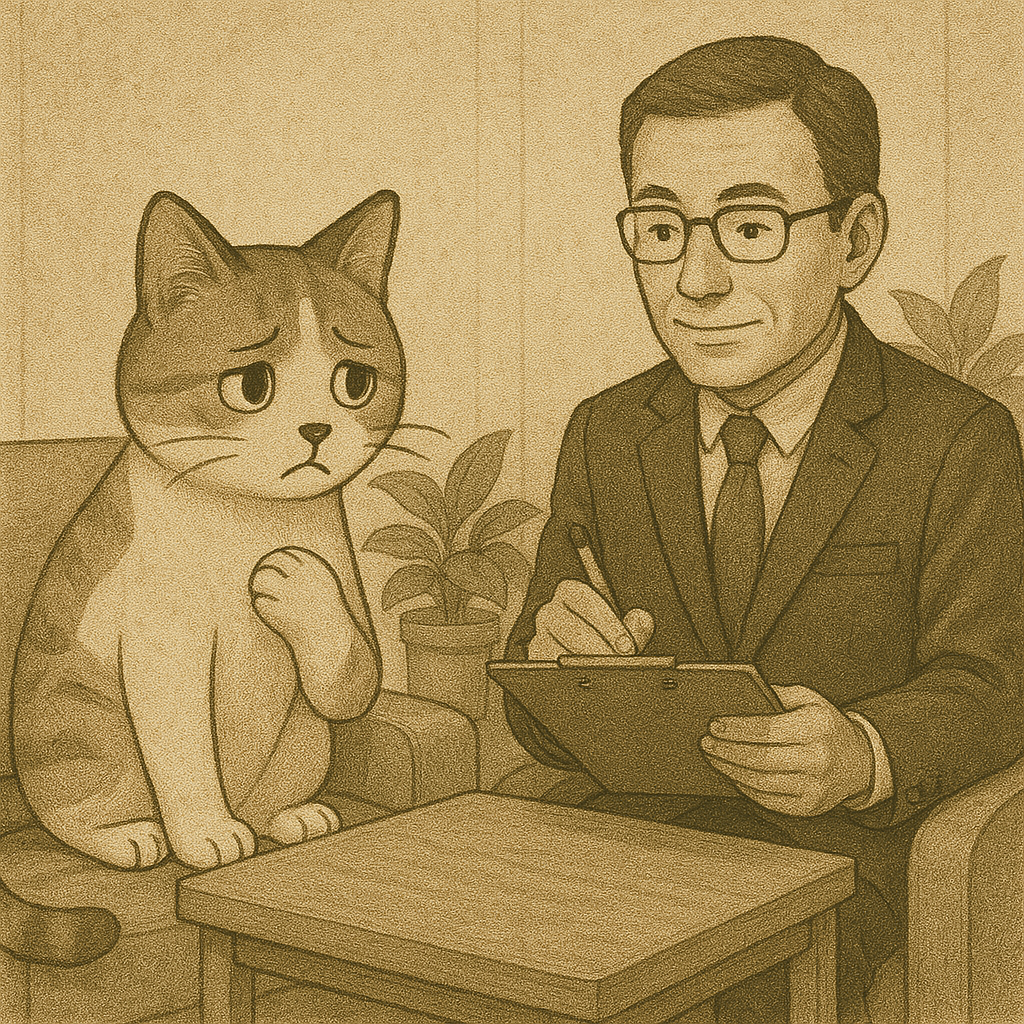
※窃盗症(クレプトマニア)という窃盗を繰り返してしまう病気があります。「もしかして自分も…」と心当たりがある方は、専門医に診てもらいましょう。これは意志の弱さではなく、専門的な治療が必要な心の病です。早めに専門医に相談することで、回復への一歩を踏み出すことができます。



コメント