Ⅰ はじめに
近時、経済環境や人員整理等を理由とする解雇事案が増加する傾向にありますが、労働者の地位を一方的に奪う解雇には、厳格な法的制限が課されております。いわゆる「不当解雇」に該当する場合、当該解雇は無効とされ、労働者の地位は原則として維持されることとなります。
本稿においては、いかなる解雇が不当と評価され得るかを概説するとともに、解雇を受けた労働者が採るべき対応手段について、実務的観点から整理いたします。
Ⅱ 不当解雇の定義と判断基準
労働契約法第16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、かつ、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」と規定しており、解雇には合理性と相当性が求められます。
また、労働基準法第19条は業務上災害による療養中の労働者に対する解雇を制限し、同第20条以下は解雇予告義務等を定めております。さらに、育児・介護休業法、男女雇用機会均等法、労働組合法等は、特定の事由を理由とする解雇を明文で禁止しております。
したがって、形式的に解雇通知がなされていたとしても、その内容や手続に瑕疵があれば、不当解雇として法的救済の対象となり得ます。
Ⅲ 不当解雇に対する対応手続
(1)事実関係の整理および証拠の収集
解雇がなされた場合、まずはその理由および時期、経緯等を時系列で整理し、以下の証拠資料を可能な限り確保する必要があります。
- 雇用契約書、就業規則、労働条件通知書
- 解雇通知書、解雇理由証明書(労働基準法第22条第2項)
- 勤怠記録、給与明細、社内通知、業務メール等
これらの資料は、後述する労働局あっせんや労働審判・訴訟等の手続において、重要な立証資料となります。
(2)行政機関による助言・指導・あっせんの活用
各都道府県の労働局には「総合労働相談コーナー」が設置されており、解雇に関する無料相談を受け付けております。また、「個別労働紛争解決促進制度」に基づき、労働局による助言・指導、およびあっせんの手続を利用することができます。
あっせん手続は非公開で迅速に実施され、使用者との話合いによる解決を図る上で有効な手段です。
(3)労働審判手続または民事訴訟の提起
話合いによる解決が困難な場合には、地方裁判所に対して労働審判申立てまたは民事訴訟提起を行うことが考えられます。
労働審判手続は、原則として3回以内の期日で審理が終結し、迅速な解決を目指す制度です(労働審判法第15条)。一方、複雑な法的争点や長期的争訟が予想される場合には、通常の民事訴訟による対応も検討すべきです。
Ⅳ 解雇無効が認められた場合の効果
解雇が無効と判断された場合、労働者は地位を失っていないこととなり、解雇日以降も労働契約関係は継続中とされます。
したがって、使用者は労働者に対して、原則として解雇日から判決日または復職日までの賃金相当額(バックペイ)の支払義務を負います。また、労働者が職場復帰を希望する場合には、原則として職場復帰が認められます。
Ⅴ おわりに
解雇に関する紛争は、事案ごとの事実関係や主張立証の在り方によって、結果が大きく左右されます。不当解雇を受けたと感じられた場合には、速やかに記録・資料を保全した上で、専門家による助言を受けることが重要です。
弁護士は、相談者の立場や希望を丁寧に把握し、適切な対応方針を共に検討いたします。お困りの際は、どうぞお早めにご相談ください。

※もちろんこんな解雇はダメです。笑


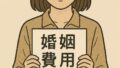
コメント